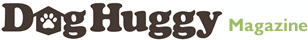2019年11月18日
【犬種図鑑】ロングコートチワワを飼う際の注意点とは?特徴と性格もご紹介
目次
「ロングコートチワワ」ってどんな犬?

日本の人気犬種ランキングで、上位ランキング常連のチワワ。チワワの中でも、耳やしっぽにあるフワフワの飾り毛が愛らしいロングコートチワワは、特に人気があります。特にマンションが林立する都市部では、超小型犬のチワワは飼いやすい犬種の一つ。
甘え上手で、飼い主のことを大好きになってくれるロングコートチワワ、そのつぶらな瞳で見つめられたら、どんなことでも許してしまいそうになります。でも、甘やかし過ぎは厳禁! ロングコートチワワを上手に育てるには、小さいころから丁寧にしつけていくことが必要です。
ロングコートチワワの歴史

古代メキシコの建造物に描かれている犬の絵は、チワワそっくり。そう、チワワの原産国はメキシコです。南米でインディアンたちに飼われていた「テチチ」という犬が祖先と言われているのですが、当時はスムースばかりでロングコートの個体は存在しなかったようです。
19世紀に入って、チワワはアメリカに渡りましたが、発見された場所(メキシコのチワワ州)の地名にちなんで「チワワ」という名前が付けられました。
当初は、スムースだけでしたが、パピヨンやポメラニアンと交配させ、ロングコートチワワが誕生し、現代に至っています。
日本にチワワがやって来たのは1970年代に入ってから。その可愛らしさですぐに人気となり、特にロングコートチワワは高い人気を誇っています。
ロングコートチワワの特徴
<特徴>
- 大きさ:超小型犬
- 標準体高:15cm~25cm
- 平均体重:1.5kg~3kg
- 被毛:ロングコート
- 被毛の色:多種多様
- かかりやすい病気:目の病気、脳障害
体型
ロングコートチワワは、超小型犬。体高は15cm~25cm、体重は1.5kg~3kgと、女性やお年寄りにも扱いやすい大きさです。
被毛
被毛は長く、からまりやすいのでブラッシングはこまめに行いましょう。カラーは、ホワイト、ブラック、レッド、クリーム、ブラック&タンなどのベーシックカラーから、ブルー、イザベラなどのレアカラー、ミックスカラーなど、実に多種多様。成長とともに毛色が変わってくるのも楽しみの一つです。
注意したい病気
かかりやすい病気でまず挙げておきたいのは目の病気。緑内障やチェリーアイがかかりやすい病気ですが、ひどくなると失明もあり得るので、おかしいと思ったらすぐに病院に連れて行きましょう。
また脳のつくりが特殊なので、脳障害も起こりやすいです。頭頂部にあるへこみがある場合、強く刺激しないことが大切です。小型犬特有の膝蓋骨脱臼にも気を付けましょう。
ロングコートチワワの性格や気質
とても甘えん坊で、常に飼い主のそばにいたがります。家族以外の人や動物に対しては警戒心が強く、怖がりな一面も! 怖さのあまり、すれ違う人や犬に吠えかかってしまうことも珍しくありません。
おうちでは元気いっぱいなのに、一歩外に出るとぶるぶる震えて、飼い主の後ろに隠れてしまう……、そんなふうにならないように、子犬のころから、積極的に外に連れ出し、色々な経験をさせてあげることが大切です。
無駄吠えしないように、また、噛み癖が付かないように、小さいころからしつけることも必要です。吠え始めたら、ひたすら無視すること。そして、噛まれて少しでも痛かった場合にはしっかりと叱ること。この2点が重要です。
ロングコートチワワの飼育方法 注意点とは
<飼育方法>
- 散歩頻度:1日1回、20分程度
- 食事の回数:2回に分ける
- ブラッシング:週2~3回
- 飼育環境:室内飼育
散歩の回数
超小型犬のため、運動量は多くありませんが、好奇心を満足させるため、また外の環境に慣れさせるためにも、1日1回、20分程度の散歩が必要です。
ごはんの量・頻度
エサは35~45gほどを、2回に分けて与えます。また骨が非常に細く、関節痛を持つ個体もいるので、グルコサミンやコンドロイチンが含まれているエサを与えるのもおすすめですよ。
お手入れの頻度
ブラッシングは、週2~3回。特に飾り毛の部分はからまりやすいので、念入りにブラッシングするようにしましょう。
飼育環境
チワワはメキシコ原産なので、ロングコートでも寒さが非常に苦手です。日本の寒さはチワワにとって寒すぎるので、寒さ対策で洋服を着せるのもよいでしょう。温度調節がしっかりできる温かい室内で飼育してください。
これからロングコートチワワを飼う方へ
生来の人懐っこさで、飼い主を魅了するロングコートチワワ。可愛らしさのあまり、ついつい甘やかしたくなってしまいますが、末永く一緒に暮らしていくことを考えると、付き合い方には注意が必要。飼い主がリーダーだとしっかり認識させることが大切です。
無駄吠えの癖や、噛みつき癖がつかないように、小さいときから丁寧に教えていくようにしましょう。
主従関係さえきちんと理解させておけば、しつけは、そう難しくはありません。叱るときは叱り、褒めるときは褒める、そんなメリハリのあるしつけで、よりよい関係を築いていきましょう。